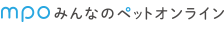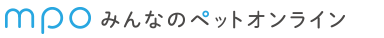ペット医療最前線
Vol.7 西洋医学と東洋医学を融合 ミシナ動物病院

院長 三科保
ミシナ動物病院 東京都豊島区要町2丁目17-3 tel:03-3972-7110
漢方というもうひとつの武器を持つ

ミシナ動物病院外観
──漢方というもうひとつの武器を持つ 東京都豊島区要町にあるミシナ動物病院の三科保先生は、西洋医学に加えて漢方薬を取り入れた統合医療で有名な人です。東洋医学的な腹診を武器に、動物の身体や健康状態をよく見ることで、もっともその患者に合った治療法を選択するべきという三科先生に話を聞きました。
おなかをさわって病気を知る

腹診から症状を判別する
──従来の獣医療に漢方薬を取り入れて十数年という三科先生は、動物の状態を見るのに「四診」という診断法を取り入れています。「四診」というのは東洋医学でいう望診、聞診、問診、切診のことで、それぞれ視覚、聴覚、質問、触覚による診察を指し、さらに切診には脈診と腹診があるとのこと。このうち、三科先生はおもにやるのは、おなかの張り具合を診る腹診だそうです。
患者さんが待合室にあふれているときに、四診全部をじっくりやっているわけにはいきませんから、来られたときの雰囲気をパッと見て飼い主さんと動物との関係をまずつかんで、それからおなかの張り具合を手で調べて診断を下していきます。もちろん、飼い主さんの話や犬の心臓の音なども聞きながらですが、これでだいたいの症状や進行度合いの判断はつきますね。
──判別の方法としては、硬い柔らかいに始まり、その強弱を五段階に分けてカルテに書いておく。おなかの弱い方が「弱」で、冷え性タイプ。この場合は守る薬(補剤)、逆の場合は攻撃的な薬(瀉剤)を使うそうで、同じ下痢でもおなかが硬い場合は半夏瀉心湯、柔らかい場合は人参湯という選択になるのだとか。
腹力って時間とともに変わるので、最初の診察時には必ず3回ぐらい診ることにしています。最初、途中、そして終わりにもう一度確認してみる。それを毎日10頭やるとすると、すごい数を診ることになるんですよ。そうすると硬い柔らかいだけじゃなくて、空気が溜まっているとか水のくちゃくちゃしている状態とかがだんだんわかってくるし、膀胱の石とか腸の癌とかまでわかるようになってきます。
──検査機器に頼るばかりで動物をさわろうともしない獣医さんがいる中で、しっかり動物に触れることで全身状態を診る三科先生のやり方は、ある意味、獣医療の根本に立ち返った診断法のようにも思えます。
漢方との運命的な出会い

補剤としての漢方薬
──三科先生は大塚敬節というお医者さんの『漢方医学』という本を読んだことがきっかけで、漢方の道に足を踏み入れたと言います。
使い始めてすぐ心臓病からくる喘息の猫が来たんですよ。いろんな西洋薬を使ってみたけど治らない。そこで麦門冬湯というのを飲ませたら、口から鼻からあぶくを吹いて、よだれをダラダラ流して倒れちゃった。それを見たときこれはもう死んじゃうかもと思った。で、とっさに飼い主さんに、覚えたての知識で『これは瞑眩(予期しない反応が起きた後、急速に症状が改善していくこと)だから心配いりません』と言ったんです。そしたら、その日の午後から嘘みたいに咳がピタリと止まった。 もし神様がいるとしたら、そのとき僕にそういう体験をさせたんだと思います。その後そんなに効いた症例はないですから。1年以上も続いていた咳がたった1回で治っちゃったんですからね。そのときはまだ漢方薬は長く飲まないと治らないというのが頭にあったんですが、一発で効くものもあるんだということを最初に教えてもらったわけです。
──しかしながら三科先生のスタンスは、すべてを漢方でやるというアンチ西洋医学ではありません。あくまでも主軸は西洋医学、そこに加えて西洋医学では打つ手がなくなった症例や漢方適用の症例に対してこれを使っていくというものです。
たとえば全体を診る目だとか、補剤というのが西洋医学の発想にはあまりないんですよ。西洋薬には抗生剤とか抗炎症剤という攻める薬が多くて、自分の身体を守ったり免疫力を上げたりする薬が少ない。漢方の場合は補剤(守る薬)と瀉剤(攻める薬)に分かれていて、守る薬が多い。僕はこの補剤の方を中心に処方して、外科手術とかの場合には当然、抗生剤やステロイドを使いますから、いわば和洋折衷の治療ということですね。
──漢方一本でも無理だし、西洋医学一本でも限界に来ているから、ちゃんぽんがちょうどいいんだと、三科先生は笑います。これはある意味、統合治療の発想に近いものといえそうですね。
洋の東西に関係なく、基本は動物を治すという当たり前のことですよね。治療法は一手段でしかないと思うんです。それがたまたま西洋流であろうと東洋流であろうと、あまり変にこだわらずにその子に一番合った方法を取ればいいと思うんですよ。
二日に一度使う薬もある

様々な種類の漢方薬
──よく使う漢方薬について三科先生にお聞きしますと…
毛がなかなか生えてこない猫がいたんですけど、その子には五苓散という利尿剤を使いました。その子はいくつかの病院で診てもらって、どこにも異常はないと言われてここに来たんですけど、血液検査では異常なしでも東洋医学的に見れば腎臓がちょっと悪かったんですね。皮膚のまわりが乾燥して毛がパサパサしてましたから、これは水の異常だろうということで、五苓散を使ったら思った通りよくなりましたね
──五苓散は腎臓病をはじめ、水の病に全部効くため第一選択としてよく使われるそうです。これと同様に、血液が影響して起こる病気には桂枝茯苓丸。婦人科系の病気である子宮内膜炎や卵巣膿腫、卵巣からくる皮膚炎などに効果がある。同じ婦人科系でも、実証タイプ(陽)であれば桂枝茯苓丸、実証タイプ(陰)であれば当帰芍薬散、気の病(精神的な面)が強い場合は加味逍遥散を使われるとか。聞いてもにわかには理解しかねますが、けっこう実用的な分類があるようです。
個人的に好きなのは十全大補湯。代表的な補剤で元気の出るやつです。これは免疫を上げ白血球を増やす効果があるので、癌の子などによく使います。いよいよ打つ手だてがないとなったときには、最後の一手といわれる真武湯。新陳代謝の低下、体温の低下が著しいときとか、半身不随だとか、手の打ちようがないときに真武湯を使って立ち直った子がいます。下痢でも水溶性の下痢が続いちゃって全然治らないなんてときには、これがよく効きます
──この他にも、膀胱結石や膀胱炎には猪苓湯、神経症や神経性胃炎などの気の病の場合には半夏瀉心湯、てんかん体質には柴胡加竜骨牡蛎湯、西洋薬ではなかなか治らない皮膚病に対しては痒みを抑える消風散や十味敗毒湯、脊髄疾患には八味地黄丸や真武湯が使われるとのこと。もちろん椎間板ヘルニアのダックスなどの脊髄疾患による運動・知覚麻痺にも、これらの漢方薬を活用されています。
あと、二日に一度ぐらいのペースで出しているのが麦門冬湯と葛根湯。麦門冬は、僕が漢方を使い始めるきっかけになった薬ですけど、今でも咳が始まったらまずこれを使います。これは喉を潤すし甘くて飲ませやすい。甘いと猫にも使えますしね。葛根湯の方は、鼻水、目の痛み、結膜炎、鼻炎など、首から上の病気全部に効果がある。だから耳がなかなか治らないとか鼻の調子が悪いなんてときにはまずこの葛根湯でやります。高齢犬の場合ずうっと薬を飲まなきゃいけなくても、これなら安心できますよね
──もちろん、こうした漢方薬の処方には最初に腹診による腹力の見極めがあって、実証タイプにはこれ、虚証タイプであればこちらという使い分けが必要で、西洋薬のようにどんな子の症状にも一様に効くというわけではないようです。
西洋薬を漢方的な発想で使うことも…

基本はあくまでも西洋医学
──これから高齢の犬猫が増えるといわれる中、一生薬を飲ませ続けなければならないとしたら、身体にやさしく副作用の少ない漢方薬----中でも補剤(守る薬)はとてもよいように思います。ただ、まったく副作用がないというのは大きな誤解で、漢方にも副作用はしっかりある。三科先生はこんな話もされていました。
小柴胡湯という肝炎の薬は、使っちゃいけない人に使うと間質性肺炎になって死んでしまったりすることがあるんですよ。こういう強い薬は使い方が非常に難しい。漢方は副作用はないというのは迷信ですよね。所詮は人間のつくったものですから、完全なものではない。使い方を誤れば毒にだって薬にだってなる。だから生半可な知識で使うべきではないと思います
──先生自身は、基本的には西洋医学をベースに診療を行い、その中の選択肢として漢方を取り入れてきたわけですが、今では西洋薬を漢方的な発想でとらえて瀉剤(攻める薬)として使うこともあるとか。
たとえばクロマイとかサルファ剤は、どちらかというと補の方に近いだろう、ペニシリン系とかセファロスポリン系は殺菌力が強いから典型的な瀉だろうというふうに分けて、抗生剤もそういう発想で漢方的治療に取り入れていく。また、ちょっとめまいがある犬で、それが耳から来たか脳から来たかわからないときに、試しに漢方使ってみるとか、そういう診断の補助に使う場合もありますね
漢方との運命的な出会い

高度医療の一つになりうる東洋医学
──西洋医学一本でやっていたときには見えなかったことが、漢方を使い始めてわかるようになってきたということもあるそうです。たとえば下痢の治療にひとつしても、本当にこの抗生剤を使っていいのかを漢方的な見地から再考するというのは日常茶飯事とか。そうした裾野の広がりは、漢方というもうひとつの武器を手にした先生だからこそ得られたものでしょう。
一般の獣医師に求められているのは、なんといっても全科診療なんですよ。最近はみなさん高度医療ばかりに目がいくようですけど、高度医療を追求するあまり専門バカになっては意味がない。私たちがやるべきは、動物たちの全身状態をよく見て、病気を表に現れている症状だけからじゃなく裏にある見えない原因から来るものとしてとらえ、じっくりそれと向き合っていく。それは漢方でやろうが西洋医学でやろうが、ホメオパシーでもなんでもいいんですよ。手段としては、おなかをさわってみたり、脈をとってみたり、顔色や皮膚の動きを見たりしてもいい。とにかく全体を見ろと。それを徹底的にやる方が、ずっと高度医療に近いんじゃないかと思うんですよ
──全体を見る。それは高度医療機器に頼る前の段階として、とても大切なことだという考えを新たにしました。
レポート一覧へ戻る獣医師への質問はこちらから
獣医師に質問する(無料)質問を探す
質問者からの声
関心の高い質問ランキング
- お知らせ
-
- 2026.02.18