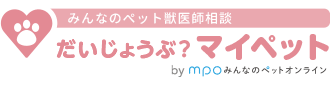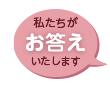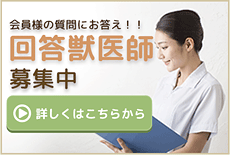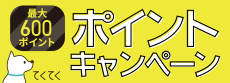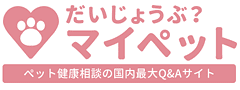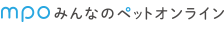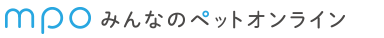井上 平太 先生の過去の回答履歴一覧|95ページ目
全2439件中 941 ~ 950 件目を表示
-
- 質問カテゴリ:
- 便・肛門の異常
- 対象ペット:
- 犬 / ラブラドールレトリバー / 男の子 / 12歳 1ヵ月
コクシジウムは一般的に猫と子犬の病気です。
成犬の場合、他の病気で衰弱していなければ、ほぼ発症しません。
ですので、あまり心配しすぎないでも大丈夫です。
以前は治療には長期間かかりましたが、今では一回の投与で駆除できるプロコックス(バイエル社)と言う薬が承認されております。
猫糞を食べてしまうごとに心配であれば、こちらの利用をお勧めいたします。
お大事にしてください。2018/01/30 00:17 -
今晩は。
輸液を毎日頑張っていらっしゃるのですね。
排尿が出来ていて、肺水腫などの循環不全が出ていなければそのまま毎日点滴を続けて頂いて良いでしょう。
その数字の推移ですとおそらく腎臓の能力は10%位に落ち込んでおり、尿の濃縮能力もかなり衰えているのではないでしょうか。薄い尿が大量に出ているはずですので脱水を防ぐためにも続けましょう。ただ、定期的に診察を受け適正な量を点滴してください。
なお、一時的に間隔は開けられるかもしれませんが、じわりじわりと尿毒症成分が上がりまた毎日点滴する日が訪れると思います。
隔日点滴にする場合には隔日にして数日後に尿素窒素やクレアチニンなどが上昇していないかどうか血液検査をして、継続できるかどうか判断すると良いでしょう。
貧血についてですが、おそらく腎性貧血だと思われます。
腎臓の大きな役割は尿を作る事と赤血球の量をカウントして少なければエリスロポエチンと...2018/01/28 00:56 -
- 質問カテゴリ:
- 便・肛門の異常
- 対象ペット:
- 猫 / ノルウェージャンフォレストキャット / 男の子 / 0歳 9ヵ月
おそらく猫回虫だと思われます。
母親猫が猫回虫に感染していると、生まれてきた子猫に母子感染を起こします。
通常は犬回虫のように胎盤感染はしませんが、母猫が哺乳中に感染いたします。
ただ、検便や虫体を拝見しないと確定できません。
便と出来れば虫体を持って動物病院へ行きましょう。
よくある事ですから心配しすぎないようにしてください。
ただ、放置してしまうと稀ですが人間にも移る危険性のある寄生虫ですので駆虫をしましょう。
お大事にしてください。2018/01/25 00:14 -
写真だけでははっきりしませんが良性の物のように見受けられます。
しかし、病理学的検査を待たないと本当の事は判りません。
主治医の先生の診察を仰ぎ、必要であればバイオプシー(細胞診など)を受けましょう。
当院では、そこに何かがある事が心配で仕方がない方の場合は、日帰り可能ですので即手術の段取りを決める事もございますが、そのへんは良く主治医とご相談ください。
中高年に起こりやすい変化だとは思います。あまり心配しすぎないようにしましょう。2018/01/06 00:50 -
ユリの種類によっては葉の一部を噛んだりおしべを飲み込んだだけで腎不全になります。
残念ながらまだ危険な品種や量は詳しく判明しておりません。
経験的にはオリエンタルハイブリッド系のユリが腎毒性が強い気がしますがこれは当院での傾向です。
動物病院で血液検査を受けて腎臓の状態を確認して頂きましょう。
投薬が必要であれば指示に従ってください。
受診は早いほど良いです。
お大事にしてください。2018/01/05 00:21 -
今晩は。
生後1か月の子犬がこの症状ではとても心配です。
この症状だけで原因は判断できかねますが様子を見てはいけません。
出来るだけ早く診察を受けましょう。
お大事にしてください。
※念のために吐物と便を持って行った方が良いでしょう。2018/01/05 00:12 -
年に二度の狂犬病ワクチンを受けてしまっても、健康に問題が出ることはございません。
狂犬病のワクチンはもともと生まれた初年度は何月に受けても年度が変わったら6月までに受けましょうと言う法律になっております。ですので、子犬は数か月の間隔で受けざるを得ない事がもともとあります。
どうぞご安心ください。2017/12/29 00:56 -
体が一定以上冷えてしまうと外気温との差から脳が誤認してしまい相対的に暑く感じてしまいます。
ちょうど熱が出た時に寒く感じる事の逆の原理です。
哺乳類は体温と気温の差が小さいと暑く感じ、差が大きいと寒く感じるのです。
冷たい床に寝そべりたがりますが、それを許すとさらに低体温になり危険です。
冷たい所に行けないように工夫してください。
お大事にしてください。2017/12/23 00:16 -
今晩は。
恵まれない猫たちのためにご尽力いただきありがとうございます。
さて、イチゴジャムの様な便との事ですが、排便回数も多くなってはいないでしょうか?
寄生虫疾患、特に何らかの原虫疾患の疑いがございます。
一過性の腸内細菌バランスの崩れだけなら良いのですが、念のため便を持って診察を受けましょう。
今後食欲や元気が消失してしまうと困りますので、子猫であれば早い方が良いでしょう。
お大事にしてください。2017/12/22 23:59 -
今晩は。
少しでも延命して飼い主の方と猫ちゃんが共に暮らすためには点滴の続行が必要です。
点滴は38から39度に調整して、点滴により体温を奪われないように気を付けましょう。
適切な量は状況により変化しますので、獣医師の指示を受けて決めてください。
しかし、いつかは点滴を止めなければならない時が訪れます。
おしっこが出ずに皮下点滴が残ってしまう場合・むくみが出始めた時・呼吸困難(肺水腫)・痙攣や嘔吐が酷く延命がかえって辛い状態を長患いさせてしまうと感じられる場合などです。
ただ、そのあたりは主治医の先生の指示を仰ぎながら考えませんと飼い主のみでの判断は酷と言う物です。
体温が下がらないように室温や保温に気を付けてお過ごしください。
猫ちゃんが穏やかに飼い主の方と時を過ごせ、一緒にお正月を迎えられる事をご祈念申し上げます。2017/12/20 23:19