- その他に関連する質問
-
対象ペット:猫 / アメリカンワイヤーヘア / 性別不明 / 0歳 6ヵ月
2025/12/23 07:11
12/14にオス猫の去勢、12/20にメス猫の去勢(1泊)しました。元々兄妹で寝る時、ご飯、トイレは同じケージを使用してて、寝る時はいつもくっついて寝てるくらいなかよしでした。
メス猫が去勢から帰ったらオス猫は... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 日本猫 / 女の子 / 14歳 6ヵ月
2025/09/26 15:45
お世話になります。
腎臓病、2.8kgの猫ですが、BUN47.クレアチニン2.2と最近上がってきてしまったのですが、薬が変わらずフォルテコール2.5mgを1日1錠のみです。
そこで、数値が上がってきたので心配でフォル... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / ロシアンブルー / 男の子 / 12歳 11ヵ月
2025/09/03 17:13
猫の瞳孔についての質問です。
最近、猫(13歳・3年ほど前から糖尿病治療でインスリン投与中)の瞳孔が大きいままだなと思い、
明るい場所に連れて行ったりライトを当ててみたりしたのですが、一応細くはなる... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 日本猫 / 女の子 / 3歳 5ヵ月
2025/08/31 17:52
3歳の保護猫を飼っています。保護当初のFCoV抗体価の数値が800でした。結果は陽性でした。
先住猫がいるので、1年間隔離していました。一緒に生活をさせることが諦めきれず、3つの動物病院に相談しました。... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / キジ白 / 男の子 / 15歳 1ヵ月
2025/08/13 10:31
1ヵ月半前に食思減退のため受診し、腎不全の診断を受けました。BUN 36.5. CRE 2.54で皮下輸液隔日150mlの指示があり なんとか続けています。
毎日行うのは私の方が辛く 隔日なので続けられています。
体重は3... 続きを見る
- 猫 / 不明に関連する質問
-
対象ペット:猫 / 不明 / 女の子 / 2歳 2ヵ月
2025/07/24 09:01
普段あまり吐くことがない猫が、ここ最近毎日のように吐きます。(1〜2日に1回程度)
嘔吐物は写真のように、餌を消化する前のもののようです。
保護してから2年ほどになりますが、嘔吐したことがあまりないので... 続きを見る
-
- 回答 0名
- 虫を食べてしまった(死骸か生きているものかは不明)
対象ペット:猫 / 不明 / 男の子 / 0歳 5ヵ月
2024/09/29 05:52
今日(9/29)の朝5時前ごろに追いかけっこをし始めたので、怪我防止のために床に置いていたものを片付けました。その際に、虫の死骸か生きていたものかわからないのですがむしゃむしゃ食べていました。朝方で部屋の... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 不明 / 男の子 / 3歳 1ヵ月
2023/11/27 23:36
11/27
口内に白いできものがあります。
似た様な他の質問者さんの写真に写されているできものよりも大きかったので質問させていただきました。
こちらはどういったできものなのでしょうか。。
ご飯を食べ... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 不明 / 女の子 / 3歳 2ヵ月
2023/03/07 11:01
はじめまして。ご相談したいことがありまして連絡させていただきました。
ずっとごはんをあげている地域猫なのですが去年の秋頃から舌が出たままになっていて、1月半ばに右耳の辺りを怪我してふらつきもひどかっ... 続きを見る
-
- 回答 1名
- 猫の治療について今後どうすればいいのか悩んでいます
対象ペット:猫 / 不明 / 男の子 / 1歳 2ヵ月
2019/05/29 11:56
よろしくお願いいたします。
1歳6ヶ月ぐらいの保護した野良猫で去勢手術した子です。
5日前に様子がおかしいので病院に初めて連れていきました、診察結果は
重度の尿毒症といわれました。
膀胱がパンパンでカ... 続きを見る
- 成猫(アダルト)に関連する質問
-
対象ペット:猫 / 茶トラ / 男の子 / 1歳 6ヵ月
2025/12/18 08:06
保護猫で、引き取った時から片方の後脚が内側に折れていて肉球が上を向いている状態でした。愛護センターの先生からは、先天的だと考えられ、日常生活には困らないため治療の必要はないと言われました。特に治療... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 雑種 / 女の子 / 5歳 1ヵ月
2025/09/04 04:31
◯猫/5歳/4.1kg/アレルギー持ち/歯肉炎で通院中/
1歳頃から突然、黒い耳垢、頭を振る、耳を掻き過ぎて出血、体も舐め壊して出血、という状態が始まりました。
病院ではアレルギーだと言われましたが、... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 日本猫 / 女の子 / 3歳 5ヵ月
2025/08/31 17:52
3歳の保護猫を飼っています。保護当初のFCoV抗体価の数値が800でした。結果は陽性でした。
先住猫がいるので、1年間隔離していました。一緒に生活をさせることが諦めきれず、3つの動物病院に相談しました。... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / ソマリ / 性別不明 / 5歳 1ヵ月
2025/08/02 10:28
約半年ほど前から、ソマリ5歳女の子体重3kg弱(避妊済み)に首周り、腰、尻尾、様々な所に人間のにきびみたいな物ができ始めました、その後かかりつけ医に相談するとアレルギーとの事でステロイド治療をし症状はマ... 続きを見る
-
対象ペット:猫 / 不明 / 女の子 / 2歳 2ヵ月
2025/07/24 09:01
普段あまり吐くことがない猫が、ここ最近毎日のように吐きます。(1〜2日に1回程度)
嘔吐物は写真のように、餌を消化する前のもののようです。
保護してから2年ほどになりますが、嘔吐したことがあまりないので... 続きを見る
猫に関する記事
記事から、グループサイト 『みんなのペットライフ』ページへと移動します。
※猫に関するお役立ち記事をご紹介しています。
猫に関する記事をもっと見る
雑種の里親募集
下の情報から、グループサイト 『hugU(ハグー)』ページへと移動します。
※猫の里親情報を掲載しています。
甘えん坊の男の子
0歳5ヶ月くらい
所在地 埼玉県
名前 まるまるくん
掲載期限2026/2/20
イケメン黒猫男子です
5歳0ヶ月くらい
所在地 福岡県
名前 くろまめ君
掲載期限2026/2/28
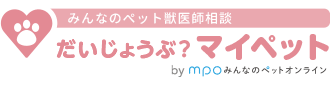
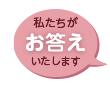
























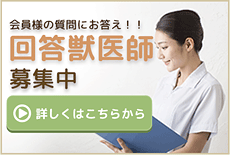




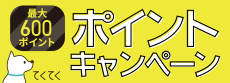
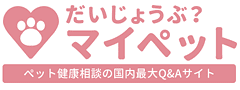
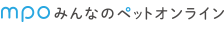

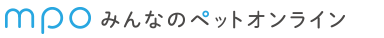
猫の処方について
猫ちゃんの処方につきまして皆様方のご助言をお持ちしております。
よろしくお願い致します。
※自己紹介
3歳 雄猫 体重4.5kg 家猫 ワクチン接種済
※相談内容概要
一年半ほど前に一瞬、目を離した隙に網戸越しに野良猫と喧嘩になり、左足の左から2番目の爪が折れて出血していました。動物病院に行き処置内容として爪の根元から爪とともに神経も切除しました。
半年ほど経過して爪が本来の爪が生える箇所ではなく本来の位置の5mmほど手前から生えてきました。
5ケ月ほど前に爪の下部に直系1cm程度の範囲で炎症を起こしているのに気づき病院に連れて行き抗生剤の投与の処置を約1ケ月半程度受けました。その後経過も良好だったため、病院に行っておりません。
(爪、周辺の炎症は収まり毛も生えてきました。出血、においもありません。爪の生え際の浸出液も収まりました。)
今月に入り、爪の生え際からほんの少しですが浸出液が見られため再度、病院を受診しました。前回受診した病院は休診日だったので違う動物病院を受診しました。
担当獣医さんの方針としては爪が本来の位置ではない箇所から生えているので異物反応の可能性があり抗生剤を1ケ月程度服用し改善が見られないようであれば、(滲出液が出るのが止まらなければ)感染を防止するため指の第1関節より切断するとの事です。
飼主としては指をなるべく残すことで下記のような治療を行いたいと考えています。
皆様のご助言をお待ちしています。
※経過
➀2022年11月(1年半前)
一瞬、目を離した隙に網戸越しに野良猫と喧嘩になり、網戸に爪が引掻ったようで鳴き声がして慌てて部屋に戻った時には左足の左から2番目の爪が折れて出血していました。(網戸がありましたので相手の猫との接触はありませんでした。)
動物病院に連れて行き処置内容として爪の根元から神経を切除しました。
半年ほど経過して爪が生えてきましたが本来の爪が生える箇所ではなく本来の位置の5mmほど手前から生えてきました。
②2024年1月(5ケ月前)
爪の下部に直系1cm程度の範囲で炎症を起こしているのに気づき病院に連れて行きまして下記の処方をうけました。(患部状況拡大写真 写真-1参照)
・抗生剤(アンピシリン)、消炎鎮痛剤(オンシオール)の注射を受ける。
・飲み薬、抗生剤(パチリオン粒)、消炎鎮痛剤(オンシオール) 約1ケ月半(3クール)
・抗菌剤のクリーム薬(ビクタスSMT)
・エリザベスカラーを装着し傷口を舐めないようにする。
1ケ月半ほど経過しほぼ治ったようでしたので、この後は病院に行っておりません。
(患部状況拡大写真 写真-3参照)
③2024年5月
ほんの少しですが傷口から浸出液があったため再度、病院を受診しました。前回受診した病院は休診日だったので違う動物病院を受診しました。下記の処方を受けました。
・手前から生えた爪の血管が残っている部分を残し爪をカットする。
・抗生剤(コンべニア)の注射を受ける。
・飲み薬として抗菌薬(ビクタスSS)、抗生剤(セファクリア)を当面、2週間分処方。
④2週間抗生剤等を服用した現在の状況
爪の生え際にほんの少しですが滲出液が見られます。滲出液は透明で匂いはありません。炎症皮膚の赤みは見られません。出血も見られません。
爪を気にする様子もありません。
エリザベスカラーはなるべく設置しています。(一日中つけているのはかなりのストレスになると思いますので、見れる時は外しています。)
※担当獣医師さんの意見方針
爪が本来の位置ではない箇所から生えているので異物反応の可能性があり抗生剤を1ケ月服用し改善が見られないようであれば、感染を防止するため指の第1関節より切断する。
改善の判断は浸出液がなくなり感染の危険がなくなったと思われる状態だそうです。
※皆様のご意見をいただきたい内容
飼主としましては最初の治療でかなり回復した事、現段階では元気に走り回っている姿を見ますと、なるべく指の切断は回避したいと考えています。
いろいろと調べてみますと人間では重症のPAD(抹消動脈疾患)患者さんに対し炭酸泉治療を行うことで下肢の切断を8割以上も回避できたとの報告など、炭酸泉治療による改善効果の報告が多数みられます。
関連記事 → https://kaikou.or.jp/touseki/strength/carbonate.html
また壊死が改善するという原理は血管が再生されているという事だと思いますが、動物実験(ネズミ)ですが炭酸泉治療により血管が再生するのに必要なVEGFやbFGFなどのサイトカインの発現を促進すると報告されています。
関連記事 ↓
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2006/0/2006_0_F0032/_article/-char/ja/
また炭酸泉がPHを酸性に傾ける効果から抗菌作用も報告されていますし、古い滲出液を炭酸泉で洗い流すことで感染予防になると考えています。
動物病院におきましては炭酸泉治療の施設がある病院は現在、それほど多くはないかと思われます。また猫ちゃんの足を炭酸泉におとなしく浸けておくのは中々困難なため、実施事例も殆どなく、現段階では一般的な治療にはなっていない(認可されていない)現状かと思われます。
幸い我が家では、近所で親戚がペットサロンを経営しており医療用と同様の炭酸泉入浴の施設を備えており炭酸泉治療が可能です。ご飯を与えながら治療することで5~10分程度、足浴が可能ですので、1日1回、5~10分程度の足浴を考えています。
実施する際は容器等、十分、煮沸消毒を実施した上で行います。
また上記と併用して1ケ月に1回程度の血液検査で炎症性マーカーを測定する事で炎症性疾患(感染)の評価をしていきたいと考えています。
猫の炎症マーカーとしまして一般的にSAAが行われると思いますが、通院する獣医師さんからは部分的炎症のモニタリング評価はSAAでは難しいと言われました。
白血球の5分類による血液検査で好中球の増加で細菌感染、外傷、壊死などの組織障害を把握できるようですが、モニタリング評価は可能ですか。
血液化学検査の項目でグロブリンが感染症で値が上昇するようですが、こちらでは
どうでしょうか。
また、できればCT撮影も定期的に行うことで感染の有無(炎症の有無)について確認していきたいと考えています。
動物(主に犬)におきましては炭酸泉治療は主に皮膚疾患の治療サポートとして行われており治療行為として現在認識されていないのは承知しておりまして猫での症例も殆どなくお答えしにくい状況は十分理解できますが、個人的な意見でかまいません。
意見をいただければ有難いです。
競走馬の屈腱炎などのリハビリにはかなり前から炭酸泉治療が行われています。
人間に馬に効果があれば猫にも効果があるのではないかと思います。
関連記事 ↓
ja (jst.go.jp)
競走馬のリハビリテーションについて:馬主の方へ JRA
上記の様に抗生剤の投与完了後、炭酸泉治療と血液検査等によるモニタリングで様子をみながら、その後の処置を決めたいと思います。
実は担当医師さんのご意見を踏まえて炭酸泉による足湯は現在、すでに実施しています。
皆様のご助言をお持ちしております。
よろしくお願い致します。