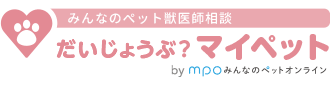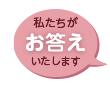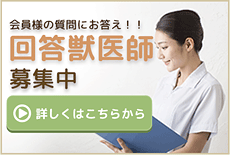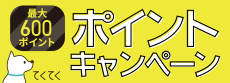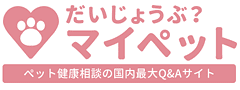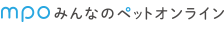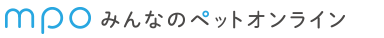栗尾雄三 先生の過去の回答履歴一覧|32ページ目
全1105件中 311 ~ 320 件目を表示
-
- 質問カテゴリ:
- 歯・舌・口の異常 / のどの異常
- 対象ペット:
- 猫 / エキゾチックロングヘア / 男の子 / 0歳 5ヵ月
獣医師の栗尾と申します。
若齢ということもあり、食べれなくなったりするレベルだとかなり心配な状況ですね。
おそらくは下顎骨の脱臼ではないかと推察されるのですが、どうでしょうか。そのあたりは触診などで確認しないとなんとも言えません。
一般的には不安定になっていると想定される関節部位を専用の道具で固定することで安定化を図ります。下顎結合が悪いのか、顎関節が悪いのかという問題な気がします。
他には神経などの問題という可能性もありますが、神経の場合は自然治癒にまかせるしかないかもしれません。
家ではとにかく食べれるものをあたえていくしかないとは思います。あとは、自分が獣医になったつもりで、顎のどのあたりが不安定なのかチェックしてあげてください。獣医師は噛まれるのを嫌って触診を嫌う先生も多々います。なので、飼い主様自身で確認してあげることも非常に重要です。
どうぞよろしくお願いいたしま...2022/09/25 20:46 -
ご連絡ありがとうございました。
少しでも参考になりましたでしょうか。
お手数ですが、以下より評価をいただけますとうれしく思います。
■以下のいずれかで評価をお願いいたします!応援していただけると大変な励みになります!
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJA1BzT_-fWjUR3MNwV2hR9S0
https://www.homemate-research-pet-clinic.com/dtl/10000000000000125018/
https://pet.caloo.jp/hospitals/detail/340232
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-zda9kPeBFwA/review/2022/09/24 18:22 -
ご連絡ありがとうございました。
少しでも参考になりましたでしょうか。
お手数ですが、以下より評価をいただけますとうれしく思います。
■以下のいずれかで評価をお願いいたします!応援していただけると大変な励みになります!
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJA1BzT_-fWjUR3MNwV2hR9S0
https://www.homemate-research-pet-clinic.com/dtl/10000000000000125018/
https://pet.caloo.jp/hospitals/detail/340232
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-zda9kPeBFwA/review/2022/09/24 09:36 -
獣医師の栗尾と申します。
おそらく再生医療というのは幹細胞移植のことを指しているのではないかと思いますが、年齢の制限は特にないとは思います。
費用については施設ごとにことなるため一概には申し上げられませんが、幹細胞移植であれば1回あたり10~25万円程度になるのではないかと推察されます。
(基本は1回だけの治療ですが、何回実施するかは個体次第です。)
多くの施設が取り扱いを始めていますが、正直、その効果はまだ未知数です。完全によくなるものではないと考えておいていただいた方がよいとは思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
************************************
konomi動物病院 獣医師 栗尾雄三
アドバイス・意見はすべて無償で行っています。
可能であれば以下より評価や感想・応援メッセージなどをお願いいたします。
■評価をお願いいたします。大変な...2022/09/23 21:42 -
獣医師の栗尾と申します。
写真を拝見いたしました。
写真の感じでは色素が薄いだけにみえます。
通常は肛門周囲はメラニン色素で黒くみえていますが、それが一部少ないというか、色抜けしているという感じでしょうか。
悪いものではない様子ですが、状態の変化など、観察してあげるようにしてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
************************************
konomi動物病院 獣医師 栗尾雄三
アドバイス・意見はすべて無償で行っています。
可能であれば以下より評価や感想・応援メッセージなどをお願いいたします。
■評価をお願いいたします。大変な励みとなります。
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJA1BzT_-fWjUR3MNwV2hR9S0
https://www.homemate-research-pet-clinic.com/dtl/10000000000000125018/
https://pet.caloo.jp/hospitals/de...2022/09/23 21:37 -
獣医師の栗尾と申します。
どう回答してよいか悩む内容ですね。
しかし、冷静に考えていただいて、いろいろやってきての今の状況なので、もう治療という意味では今以上にできることはないということだと思います。
明らかに弱り、衰弱して、命が尽きていくのをみていくのは我々、獣医師でもとてもつらいものです。私自身も何度もそういう経験をしてきました。でも何もできない状況というのはどうしてもあります。受け入れて、すべてを飲み込んで、覚悟するしかありません。
申し訳ございませんが、気持ちの問題かと思います。
具体的に○○という薬を使ってみましょうなどと安易なことは言えそうにありません。
餓死というのはちょっと厳しい言い方ですが、病気で痩せて細って、栄養失調になってしまうことは人間の医療でも当たり前にあることです。そういうものなのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
*************...2022/09/23 21:35 -
獣医師の栗尾と申します。
CRPの高値が手術による影響ということも考えられますが、手術より1週間以上経過していますでしょうか?
もし、1週間以内であれば手術によって炎症反応が出ているだけとも考えられます。
また急性膵炎や胃腸炎の主症状は嘔吐、腹痛などですが、いかがでしょうか?食欲がない、下痢だけなどであれば、あまり膵炎などは検討されません。
あとは急性膵炎という結果が出たというのは血液検査ででしょうか?血液検査でリパーゼなどの数値を測定する必要があります。
急性膵炎の際には絶飲食を含む飲食制限、点滴などの治療の他、制吐剤などの投薬が必要になります。時には命にかかわるケースもありますので、注意が必要です。私の場合は入院をすすめることも多々あります。
どうぞよろしくお願いいたします。
************************************
konomi動物病院 獣医師 ...2022/08/21 20:39 -
ご連絡ありがとうございました。
少しでも参考になりましたでしょうか。
お手数ですが、以下より評価をいただけますとうれしく思います。
■以下のいずれかで評価をお願いいたします!応援していただけると大変な励みになります!
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJA1BzT_-fWjUR3MNwV2hR9S0
https://www.homemate-research-pet-clinic.com/dtl/10000000000000125018/
https://pet.caloo.jp/hospitals/detail/340232
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-zda9kPeBFwA/review/2022/08/21 17:06 -
ご連絡ありがとうございました。
少しでも参考になりましたでしょうか。
お手数ですが、以下より評価をいただけますとうれしく思います。
■以下のいずれかで評価をお願いいたします!応援していただけると大変な励みになります!
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJA1BzT_-fWjUR3MNwV2hR9S0
https://www.homemate-research-pet-clinic.com/dtl/10000000000000125018/
https://pet.caloo.jp/hospitals/detail/340232
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-zda9kPeBFwA/review/2022/08/21 17:05 -
獣医師の栗尾と申します。
門脈シャントは程度により血液検査の結果はさまざまです。
状況的には門脈シャントの可能性は低いように思えますが、可能性がゼロというわけではなさそうです。
ただ、確かに多飲多尿を治療する意味で門脈シャントの手術をするというのは微妙な選択かもしれません。仮に門脈シャントがあったとして、手術などで治療をしても多飲多尿が改善するという見込みがどれほどあるかは不明です。
多飲多尿・尿漏れの場合
①膀胱炎
②腎臓病
③糖尿病
④栄養性
⑤尿崩症
⑥炎症性疾患
⑦精神的なもの
⑧筋肉の問題(尿漏れに限り)
などでしょうか。
個人的な経験ですが、2歳という若齢での場合は、栄養的な問題や精神的な問題であることがほとんどではないかなと感じています。
ミルクやビタミン豊富な栄養補助食品を与えていると水をよく飲むようになります。
あとは、興奮気味だったり、常にハイテンションな子も水を...2022/08/19 19:05