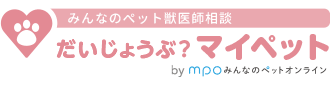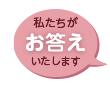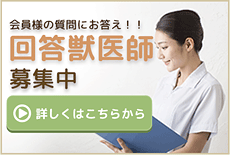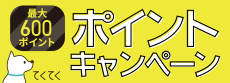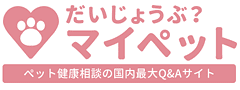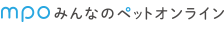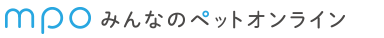伊東 彰仁 先生の過去の回答履歴一覧|38ページ目
全1207件中 371 ~ 380 件目を表示
-
先生の言うとおりです。
慢性腎不全は、腎でろ過して排泄されるはずのタンパク質の分解産物のBUNが、排泄できなくなって血中に蓄積することにより症状がでます。
うちでも、食欲がなくなったら、出るまで(平均3日ほど)入院点滴で、次に症状が出るまで、自宅という繰り返しです。このインターバルは、次第に短くなってゆきます。治る病気ではありません。食事も、淡白含有量の少ないもの(処方食)を与え、吸着剤や、淡白同化ホルモンなどを使いますが、点滴を入れて、ろか率の低下を循環量でリカバーするのが良いでしょうね。
行きたがらないからといってほおっておくと、さらに機能障害が進行して、点滴入れても食べなくなってしまいますよ。2006/06/30 11:46 -
回虫はもちろんおうちへ来る前の、いずれかの段階で感染したものです。胎盤で感染した仔虫とだけとはいえません。来る前の環境が粗悪であれば、生後2ヶ月の間に感染したものということも考えられます。
回虫は、そんなに難しい虫ではありません。確かに薬によっては、個体差があって、落ちないケースもありますが、種類を変えてやれば、まず問題ないです。しかし体内移行期には効きませんから、3~4週後に、必ず再駆虫を行ってください。卵が検出されるということは、成熟した虫がいるわけですから、駆虫は初めからです。
回虫は、人にも感染して、犬よりも問題が起きる、人獣共通感染症です。糞便の後始末や、過剰な愛情表現(キスなど)は避けてください。2006/06/30 11:38 -
- 質問カテゴリ:
- 便・肛門の異常
- 対象ペット:
- 犬 / ゴールデンレトリーバー / 性別不明 / 年齢不明
積極的に腫瘍と戦ってゆくか、QOLの改善にのみ努めて、命を終わらせるか、まずははっきり決めるべきです。
状況ははっきりしませんが、書いてあることから察するに、かなり進行しているものと想像できます。
飼い主さんの意向をもっとはっきりさせておくべきではないでしょうか?
大きさ的なリスクが大きいのであれば、オペで摘出するべきでしょうし、オペが出来ない(麻酔の危険性が高すぎて、かけられない)というケースでは、おそらく化学療法も、リスクがあって無理でしょう(麻酔のほうがリスクは少ないと思っています)。
進行がんの場合、でも取れる手立てとしては、効き目に大きなばらつきがあるものの、最近流行りの免疫療法なども望みを繋げる方法の一つです。
うちでは積極的に取り入れていますが、延命効果と、QOLの改善には、一役買っています。2006/06/30 11:15 -
まだ生後2ヶ月で、しつけは無理です。
それから、躾は褒めるか褒めないかでであって、褒めるか叱るかではありません。
おそらく、飼い主さんの「こら!!」は、褒めているのとあまり変わらないことを認識してください。
甘がみも、本気で咬んでいるのも、基本的には同じです。
咬むことすべてに対して、同じ反応で接したほうが、分かりやすいと思います。
すべて○かすべて×なのです。
よく対応が分からなければ、専門のトレーナーや、しつけ教室で相談することです。咬み癖の躾は、一歩間違うとエスカレートさせるだけの結果になってしまいます。2006/06/30 11:05 -
犬は、視覚以外の感覚には人に比べて長けていますので、聞こえているか聞こえていないかの反応は特に難しくありません。
むしろMRIで、その判断をするほうが難しいと思いますよ。
MRIで分かることというのは、物理的に何かあるかないかということで、感覚器の感度特性が分かるわけではないのです。
むしろおうちでぐっすり眠っているときに、誰も動かずに、名前を呼んでみてはいかがでしょう。
耳も動かず、ピクリとも反応がなければ、両耳の聴覚障害を疑います。
しかし、家庭犬で、聴覚障害がある場合、別にストレスにはならないはずです。音のない世界は、きっと快適だと思います。よく寝られるし、神経質になることもないでしょう。本人にとっては、視覚や嗅覚に比べて、問題は少ないでしょうね。
ただし外耳道炎や、内耳前庭の異常は、痛みや痒み、悪心や、平衡感覚の異常、見当識障害など、問題となるものも多いので、病気は病気、ちゃん...2006/06/30 10:55 -
初めて接種したときには、身体には抗体がないのが普通です。一種の異物ですが、身体の反応はそのタンパクを読み取り、そのタンパクに特異的な抗体を作ります。しかしその量(抗体価といいます)は低く、すぐに落ちてしまいます。そこで免疫が応答したあとに、改めて同じものを接種すると、もともと型が合いますので、身体の免疫機構は多くの抗体を産生します。これをブースター効果というのです。
ですから成猫でも、1回でいいということはありません。初年度は3~4週あけて2回接種します。
犬の狂犬病のワクチンは1回で・・・・・というかもしれませんが、海外に出る、また海外から入れるという場合は、1ヶ月あけて2回接種するんですよ。国内に発生がないので、2回目は翌年なんて方法をとっているだけです。決して、子猫は免疫が弱いから二度打つというわけではないのですよ。2006/06/25 11:37 -
- 質問カテゴリ:
- その他
- 対象ペット:
- 犬 / ミニチュアシュナウザー / 性別不明 / 年齢不明
まずワクチン時期ですが、早い時期からのワクチンは意味がないだけではなく、免疫がつきにくくする原因にもなります。身体で免疫を作ることができる機能が完成されるのが、生後6~7週齢です。これ以前にはワクチンを打つべきではないでしょう。それと、初年度の最後ですが、生後17週齢以降に打つことです。これは通常混合ワクチンを使用していますから、親犬からの移行免疫が最長パルボウイルスの113日齢ですから、これ以降に打たなければなりません。通常ハイリスク環境(別環境の犬の出入りが多いところ:ケンネルなど)では、初回を7週から始めて3週毎に繰り返して、17週かそれ以降まで打ちます。
ローリスク環境(詳細不明な犬との接触のない環境:家庭)に移ってからは、5週ごとに繰り返して、17週かそれ以降まで打ちます。回数は最低2回は打たなければなりませんが、感染リスクを下げるということで、3~5回繰り返し接種します。た...2006/06/25 11:27 -
不正咬合による歯石の付着と、当たる場所によっては口内炎などでしょう。主にあるとすれば美観の問題です。
繁殖に供することは避けてください。2006/06/25 10:56 -
食糞したので下痢をしたというわけではありません。むしろあるとすれば、しょっちゅう下痢をすることの原因が食糞につながっているかもしれません。(そうでない場合も多いのですが)
回虫などの寄生虫感染や、ある種のミネラルの不足から食糞が起こることも知られていますが、むしろ餌が合わない可能性が大いに考えられます。餌を幼犬用の消化器系用処方食に代えていただきましょう。それで2週間やっても変わらなければ、分子量を下げたかたちの、抗アレルギー食をやってみてください。もちろん水以外は一切だめです。(おやつは無しですよ)2006/06/24 13:58 -
①褒めてあげるべきことです。トイレでしているのですよ。
これでは困るのなら、もっともっと大きなトイレでさせてあげるか、大きなトイレの中に、今のトイレを置くかしてください。
②具合は悪くありません。確かに缶に比較して嗜好は落ちますが、この仔はちゃんと食べているようなので、問題なしだと思います。ここで元に戻したり、いろいろなもので試すのはやめてください。食事中はサークルを閉めて運び出せなくすれば良いのでは。餌の量が多すぎてはいませんか?通常缶などの餌に比べて、乾燥している状態のドライフードは、2~2.5分の1程度です。分からなければ、ドライフードを最高にふやかした状態と量比較をすればわかります。2006/06/24 13:50