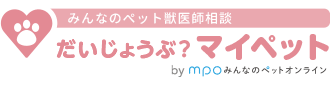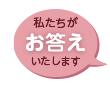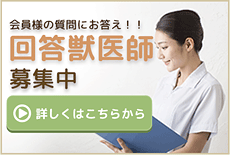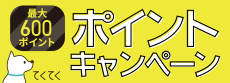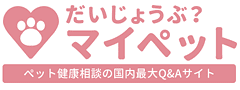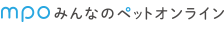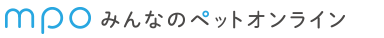北森 隆士 先生の過去の回答履歴一覧|36ページ目
全914件中 351 ~ 360 件目を表示
-
フィラリアは、小虫から成虫になって心臓に住み着くまでに
~数ヶ月から1年、心臓に住み着いて、フィラリア症を発症させるまでに数年かかります。
先生によっては、医療経済的な立場から(つまり、もう数年は、生きないのだからと言う立場)、お薬を止めるように助言することは、まま、あることだと思います。
確かに、現時点での獣医学が扱う疾患は、最終的なフィラリア症です。感染初期の小虫が体内でどのような悪さをしているかについては、実は誰もわかってはいません。しかし、感染が成立しているのは確かですから、体にとって良いわけはありません。また、もしかしたら、症状が目に見えないだけで、体内でとんでもないことがおこっているかもしれません。
フィラリア薬は、24時間で速やかに体内から排泄されるので、体への負担はほとんどありません。寝たきり状態で、食事もとれない末期であれば別でしょうが、健康状態も良いのであれば、...2007/03/10 10:21 -
そもそもの原因は、なんでしょうか?
また、原発巣(もともとの発生場所)は本当に薬指ですか?
何か異物が刺さっている可能性や、原発巣が他にある場合が
あります。
また、ネコで、なかなか化膿が収まらない原因として、
骨に化膿が波及している場合、エイズ・白血病といった
感染症が背景にある場合、糖尿病や腎臓病などの疾患が
併発している場合もあります。
一度、血液検査やレントゲン検査(もうしましたか?)
をしてみては如何でしょうか。
いずれにせよ、食欲もなく痩せてきました・・・・のは
よくありません。2007/03/10 10:10 -
>老犬に処方するとそのまま死んでしまうかもしれないとこ
確かにそうですね。ただ、人間の生活あってのイヌです。人間が
参ってしまえば、もともこもありません。そういう場合は、内臓の機能を確認し、問題なければ、処方することもあるえます。クロミカルムは、即効性もなくあまり効果はないと思います。血液検査をして、問題なければ、思い切って、催眠薬系のお薬をしようしてみるのもよいかもしれませんね
>は無駄吠えです。夜鳴きは2年ぐらい前からあり夜中2回ぐらい外に出したりして治まって
どうしてもも場合は、声帯を取る手術をおこなうことが
あります。この手術で、無声にはなりませんが、声が
かすれて響かなくなります。無論、全身麻酔下ですから、
リスクはあります。また、年齢にもよりますが、半年
ぐらいで、声帯が再生することがありますが・・・・・。2007/03/05 20:08 -
- 質問カテゴリ:
- 対象ペット:
- 犬 / ミニチュアダックスフンド(ロング) / 性別不明 / 年齢不明
逆くしゃみは、発作性の、激しい努力性吸気(息を吸うこと)状態を指します。おそらく横隔膜と肋間筋収縮の繰り返しが症状の発生機序と考えられています。原因としては、鼻咽頭疾患、異物、鼻洞疾患が考えられています。まずは、症状を出来る限り細かく担当の先生に知らせて、本当に逆くしゃみ現象かどうかはっきりさせることが重要です。
>発作を出にくくする方法や成分、食べ物など・・・
>あれば是非とも教えていただきたいと思います。
喘息性の発作ではないので、とくに引き金になるような
食べ物、物質は報告されていません。
どちらかというと、ヒトで言えば、過呼吸のような
症状です。
>発作のときは、愛犬が苦しそうで見ていられません。
もし逆くしゃみであれば、外鼻孔(鼻の穴)を一時的に
塞いで、咽頭部(のどの付けねの部分)をマッサージして
上げると治る場合があります。
また、私は実際には行ったことはあり...2007/03/03 17:30 -
このサイトでも何度も言っていますが、世間の方は、
イヌの椎間板ヘルニアをヒトと同じように考えておられます。
とても危険なことです。
いいですか、イヌのヘルニアは半身不随まで進行する場合が
あるのですよ!
人の椎間板ヘルニアとイヌのヘルニアはまったく
症状、重傷度が違うのです。イヌでは、神経の
太いところが圧迫されるため、下半身不随に移行する
ことが比較的多いのです。つまりどちらかというと、
人の交通事故の脊髄損傷に近いのです。ヒトでは安静に
していれば軽症ならば治りますが、イヌは半身不随まで
いくのです。ぜひ、ぜひ覚えておいて下さい。
治療効果がはっきりしているのは、手術と、ステロイドです。
ただし、ステロイドは、重症のものにはききません。
電気やレーザーは、慢性化している場合には確かに
痛みが緩和するときもあります(当院でもそのような
治療はしています)。しかし、発症時に...2007/03/01 18:57 -
ワクチンは同時に接種しないほうがよいと思います。
おそらく、学問的には同時に接種しても有効性は得られるでしょうが、副作用のことを考慮すると・・・例えば混合ワクチンで体調が悪くなったところへ狂犬病を打つということですから・・・・・・・良くありません。
ワクチンのなかには、少なからず体を刺激するような不純物が
入っていますが、2つのワクチンを同時に接種するということは、その不純物を同時に2回(2倍)接種するということで、良くありません。
確かに日本でも十数年前までは同時に接種していましたが、上記のような安全性の問題から、分けて接種するのが主流です。
数週間は離してください。
2007/03/01 10:49 -
耳血腫は、非常に発生率が高いにもかかわらず、なかなか治るものではないので、獣医師なかせです(すぐ治る子もなかにはいますが・・・)。治り辛いのは、特定の原因による疾患ではないからです(免疫の問題、耳の形状、痒み、性格・・・・・など)。ちなみに当院では、1年も再発を繰り返した子がいました。
米国では、耳を短く切除する手術もあります。耳がなければ
ならないという、彼らの合理的な考えですが、それくらい
治り辛い疾患なのですよ。
>不安と腹立たしさとで頭の中がいっぱいです。
不安なのはわかりますが、腹を立てるのは良くありません。
病気は、先生の個人の力ではなく、獣医学が治しています。
その獣医学がまだまだ病気を解明していないとしたら、それは
先生の責任ではないでしょう?
問題があったとしたら、
『手術で絶対に治ると思わせた先生』のそのインフォームに
あるのでしょう。ただ、言葉というのは、な...2007/02/28 19:39 -
当院では、イヌ、ネコのワクチンの臨床試験を行っていますが、ネコの場合、上記の区別がなかなか難しいところがあります。
ワクチン接種後の元気食欲低下は、ワクチンアレルギーに
よるものと、単純に接種部位の痛みによるものに大別され
ます。ネコは繊細なところがあって、少しの痛みでも固ま
ってしまうので、その区別が難しいのです。
ちなみにアレルギーの場合は、顔が腫れたり、全身性の症状
(呼吸が荒くなったり、全身の皮膚になにかできたり)が出たり、かなりかなりかなりかなり稀ですが、死亡例もあります(
ヒトのインフルエンザのワクチンだって死亡例があるくらい
ですから、ワクチンというものはそういうものです)。
さて、今後どうするかですが、
完全室内飼いであれば、7種ではなくて3種でも十分だと
思います。3種は、7種と違って、痛くなるような成分が
少ないので、もしかしたら接種後の異常が軽減されるかも
...2007/02/28 11:11 -
米国では7~8週齢程度の子で手術する病院もあります。
そしてそのような早期の手術は、一般的な7~12ヶ月齢程度の
子の手術と比較して、成長(体格、体重)や疾患発生率
などに変化はないという見方が現在体制のようです。また、余
談ですが、面白い事に、早期手術で逆に骨の長さが若干長くなるという研究もあります。
>早い時期に去勢をすると、体が大きくならずに肥満になると聞きました
そんなことはありません。成長後手術しても、同一カロリー
で管理すれば、肥満になります。
まあ、だからといって、どうしても早く手術をする必要が
あるわけではありません。先生の慣れもあります。健康な
子にあえて手術をするわけですから、学術的な背景に「加え、
先生のやり方と、あなたの気持ちが一致したときがベストな
時期でしょう。
2007/02/27 21:09 -
色々考え方はありますが、ドライフードだけでも治療効果はあります。どうしてもドライフードしか食べず、飲水量も少ない子には、ドライをメインにして、注射筒などで強制的に十分量を飲ませる方法もあります。
(ところで、ちゃんと絶食時間を設けていますか。だらだら食いは、それだけで尿石のリスクを上げますよ。ご存知でしたらすみません。)
>、白血球や蛋白の数値がなかなか良くならないので他の療法や検査
慢性経過の膀胱炎は、完治するのに数ヶ月を要することが
しばしばです。ネコさんが暴れなければ、例えば膀胱の
エコーで粘膜面の状態を確認することは必要かもしれません。
また、長期に抗生物質を使用する場合には、肝機能等の
検査も必要かもしれません。しかし、「いずれにせよ、慢性
の膀胱炎・尿石症の治療は、どの獣医師も悩むところです。
先生とよくお話をして、じっくり直してください。
2007/02/27 17:50