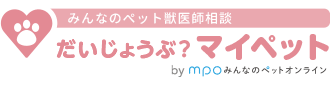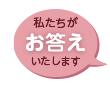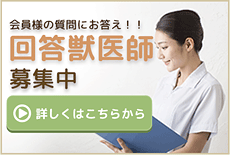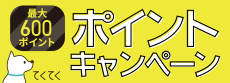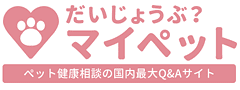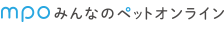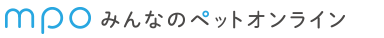井上 平太 先生の過去の回答履歴一覧|142ページ目
全2439件中 1411 ~ 1420 件目を表示
-
- 質問カテゴリ:
- 皮膚の異常
- 対象ペット:
- 犬 / ラブラドールレトリバー / 性別不明 / 年齢不明
肥満細胞腫は非常に理解しにくい腫瘍の一つです。肥満細胞腫は大きく分けると未分化型・分化型・その中間の型に分かれます。今回はそのうちの分化型という事でしょう。なお、針細胞診は熟練した病理学者でも正答率はそれほど高くございません。きちんとした生検は、正しい選択だと思います。しかし、この腫瘍は、長い事成長に変化のなかった物が突然大きくなり浸潤や転移を始めたり、再発がかなり濃厚に疑われているのに天寿を全うするまで全く動かなかったり予測が困難なのも事実です。突然に豹変する腫瘍なので臨床家はおおむね悪性と考えて手術にあたることが多いものです。
手術を行う場合には十分に腫瘍から離れて切開していくことになります。この腫瘍はインクのシミのように境界線がはっきりいたしません。そこでできるだけ天然の隔壁を利用して摘出を行います。(たとえば筋膜をくっつけて摘出すること)しかし、十分な距離がとれない四肢や尾...2009/07/24 23:24 -
うーん・・・私も昔犬に生理痛はないと飼い主の方に言ったことがあるような気がしてきました。確かにすべてを含めて発情期にありえる症状として説明しておりますが、犬はその事を訴えられないだけで、食欲不振は下腹部の鈍痛が原因かもしれないし、よく鳴くようになるのは頭痛があるのかもしれません。落ち着きが無いのは精神的苦痛の表れなのかもしれません。
この場をお借りして謝罪いたします。
このような発情症状が強い子は経験的に乳腺腫瘍・乳腺炎・偽妊娠・子宮蓄膿症・・・等の発症率が高いような気がいたします。
一度診察を受けてみて他に原因が無ければ、避妊手術お受けることもご検討ください。
お大事にしてください。2009/07/23 01:19 -
今晩は。
我々の用いる言葉の中に「様子を見ましょう」というフレーズがあります。非常に誤解を招きやすい言い回しなことは重々存じております。また、このような対面ではないネット上で使うのは誤診のそしりを受ける可能性があることを承知の上で、あえてこの場合「様子を見る」のが、得策のような気がいたします。
ネット上では我々にはこの子がどの程度のリスクがある肝臓病かは、うかがい知ることはできません。しかし、実際に診た獣医師が手術の延期(中止?)を最善と考えたのであれば、それ相応に肝機能が悪化しているものと思われます。
手術の必要性の有無をを天秤にかけてどちらを選択するかを考えるのであれば、肝臓の薬を投与しながら様子を見てはいかがでしょうか。その間の腫瘍の成長スピードを観察して、その情報も加味して判断するのが良いでしょう。
病理検査を行いますとより判断を客観的に行う事ができますので、主治医...2009/07/23 01:03 -
- 質問カテゴリ:
- 便・肛門の異常
- 対象ペット:
- 犬 / ミニチュアダックスフンド / 性別不明 / 年齢不明
今晩は。
下痢に関しては、我々も原因がすぐに分からず、治療に時間がかかる例にしばしば遭遇し、いつも悩まされております。飼い主の方のご不安はそれ以上だと思います。
下痢と一言で言っても、単純な消化不良・ウィルス感染・細菌感染・寄生虫感染・食物アレルギー・吸収不良症候群・炎症性腸疾患・腫瘍など他の病気の症状として・・・など色々な原因がございます。
今回のお話をお聞きいたしますといずれかの免疫の介在するタイプのような気がいたします。食物アレルギーや炎症性腸疾患がまっさきに思い浮かびます。それに合わせた食事療法や免疫抑制剤の投与が必要なのかもしれません。
いずれにせよ数回の診察によってはじめて診断できるものですので、じっくりと腰を据えて診療に通ってください。
お大事にしてください。2009/07/21 23:48 -
一回の診療では診断がつかないことはよくあることです。特に痛み止めを服用した結果がどうであったかは、主治医の先生にとって重要な情報です。その事によって次に来院した時に何とかして検査をするべきなのかどうかを判断する事になると思います。あるいは次に試みる薬が既に決まっているのかもしれませんよ。
痛みなのか痺れなのか・整形外科的なのか内科的疾患なのかは慎重に判断されていくものと思われます。
拝見していないのでいい加減なことは言えませんが、状況によっては麻酔をかけてでもレントゲン検査を行うべきなのかもしれません。
お大事にしてください。2009/07/21 00:56 -
今晩は。
飼い主の方が認識されておられるとおり、とても重篤な病気です。しかし、乳び胸は病名というよりも結果でございます。原疾患が無いかどうか詳しく調べることが重要です。対症療法としての胸腔内の乳びを抜くことはとても大事ですが、原因がある場合にはそれを治していかなければいけません。
原因としては稀に外傷が原因である事がございますが、腫瘍・心臓病・肺捻転などが原因となる場合がございます。しかし残念ながらかなりの患者さんが原因不明です。
Ⅰ 治療法
①低脂肪食により乳びの発生を抑える。
②原疾患があればそれを改善する。(心臓の治療など)
③肺側の胸膜と肋骨側の胸膜を癒着させて貯留出来なくする。
④開胸して胸管を結ぶ。
⑤その他諸々の手術法。
Ⅱ 家での注意
①安静が第一です。
②必要があれば酸素テントのリースを受ける。
③食欲がない場合には胃チューブを装着して流動食を...2009/07/21 00:42 -
一番可能性が高いのは、てんかんだと思います。しかしこれに関してはもう少し詳しくお話を伺わなければなりません。
てんかんは、ほとんどの場合は原因不明です。レントゲン・CTスキャン・MRI等に変化は認められない事が多いです。しかし、ごくまれに水頭症や脳腫瘍や頭部打撲などが誘因になって起こることもございます。
お薬によって起こらないようにコントロールすべきかどうかは、発症頻度や症状の強さで考えていきます。月に何度も起こったり、筋肉の硬縮が長く続いて体温が上がってしまうようであれば内服薬で発作の予防を図るべきです。経過とともに頻度が増すようであれば精密検査が必要です。
発作の持続時間やいつ起きたかをしっかり記録しておくこととその様子を動画に撮っておくことが大事です。次に起きた時にも診察を受けた方が良いでしょう。その時に記録を見ていただくとよいでしょう。てんかんの維持に必要な薬の種類や量は個々...2009/07/18 12:59 -
発症の経緯から考えますと、一番疑わしいのはてんかんの一形態である焦点発作かもしれません。
焦点発作は部分発作(てんかん)ともいわれております。主な症状は突然の硬直・金縛り状態・誰にも見えない幽霊のようなものをじっと見つめるしぐさ・いないはずの虫を噛みつく動作・などです。
非日常的な環境が引き金になることもございますし、なにも思い当たらない場合も多いでしょう。意識がある場合がほとんどですので、飼い主や獣医師もてんかんと思わずにただの癖だと思ってしまう事もございます。
頻度が少ない場合には無処置で良いですが、度重なるときは抗てんかん薬を服用すると発症頻度を減らせます。
もちろん拝見せずに答えておりますので、見当違いかもしれません。また起こるようであれば動画に撮っておいて獣医師に診せるとよいでしょう。
お大事にしてください。2009/07/16 23:22 -
①4カ月かけてゆっくり感染が顕在化したと思われる。
人間の手を介して感染する可能性はあり得るが非常に低い。
②回虫は親から感染したものが今回の注射により駆虫された可能性が高いでしょう。
なお、疥癬は人によってはそれにかかっている猫がいる部屋に入るだけで皮膚炎や鼻炎や結膜炎をおこす場合がございます。しかし、これは感染とは別で、アレルギー反応です。罹患猫に触れた時に一時的に人の皮膚上にうつり、日和見的感染を起こすことはございますが。しかし、猫同様の持続的感染を起こすことは稀です。
お大事にしてください。2009/07/13 23:46 -
- 質問カテゴリ:
- 皮膚の異常
- 対象ペット:
- 猫 / ゴールデンレトリーバー / 性別不明 / 年齢不明
皮膚病の診断にはある程度時間がかかります。アレルギー・カイセン症・表在性化膿性皮膚炎・自己舐性の皮膚炎・真菌症・・・すべて文章にすると症状はかさぶたと脱毛になってしまいます。
皮膚の鏡見は何度か行わないと結果が出ないことがございますし、真菌培養を行わないと判断できないこともございます。食物アレルギーですとアレルゲンフリーの食事を半月以上続けてみないと判断できません。特にアレルギーは、今はやりのIgE検査のみで全てが判るわけではございません。
根気よく通院してください。お大事にしてください。2009/07/09 00:46